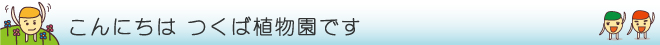
<<前年 | 翌年>>
<< 2022年11月 >>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 11月29日(火) 合体!変形!サトウキビ圧搾器が完成!
- 屋外栽培班の二階堂です。
サトウキビを圧搾する道具を制作しました。
一号機(圧搾受け部分)、二号機(圧搾加圧部)、三号機(圧搾部分を動かすテコバール)が合体変形します。
①一号機を二号機に乗せる(パイルダーオン!)。
②一号機から圧搾した糖液が流れるベロを出す(シュババッ)。
③二号機の圧搾加圧部を反転して一号機の圧搾受け部分に乗せる(ガゴオオーン!)。
④三号機のテコバールを二号機の圧搾加圧部に差し込む(ズギューム)
使う時は一号機の圧搾受け部にサトウキビを置いて、二号機の圧搾加圧部を三号機のテコバールで上下させてジワジワ絞り込みます(グワーン、ズワーン)。
先日の試運転では、ちゃんと搾れました!
これがどんなふうに活用されるかって?!
今後のお楽しみです!!
ページトップへ
- 11月25日(金) マンドイレク展示
- 今年は例年より早く開花したので、サバンナ温室にて展示しています。
この株の根の様子はこちら。9月始めに植え替えた時のもので、その時のレポートを紹介します。
------
「今日はアイツを植え替えるよ!」と教えてもらい、現場に立ち会ってきました。
アイツとは・・・そう、
「人間の形によく似た根を引き抜くと根が悲鳴を発し、これを聞いた人は命を落とす」
と言われる伝説の植物、マンドレイクです!
何年も前から根の姿を生で見たい!と楽しみにしていて、ようやく念願叶いました。
聖書時代から知られる西洋文化で最も有名な薬用植物の1つで、
魔法や魔術などと関連づけられることの多いマンドレイク。
春ごろから休眠し、夏の終わりに新芽が動き出すので、植え替えの絶好のタイミングです。
温室のコバヤンが慣れた手つきで鉢から根を取り上げてくれました。
ひゃーっ!と悲鳴をあげたのは私だけでした・・・。
かなり根が大きくなり、人のような形ではなくなっていますね。
悲鳴というより「見ちゃいやーん」とくねくねしているように見えます、という人もいました。
------
展示は12月初旬くらいまでの予定です。
花が終わったら再びバックヤードに戻しますので、この機会をお見逃しなく!
ページトップへ
- 11月24日(木) 腰道具シリーズ⑤ ★各栽培員が使っている腰道具類を不定期で紹介します★
- クレマチス園やバックヤードで植物たちのお世話をしているО内です。
このブログでは初めましてです。それでは普段使っている道具を紹介します。
ハサミはアルスコーポレーションのクラフトチョキ。前職の花屋時代からここのハサミを使っています。刃先が細くて使いやすいです。植物を切るだけでなく、用土の袋やビニールの紐なんかを切るのにも使っています。
作業中にどこかに置き忘れたり、ごみに紛れて失くしたりしないようにビヨーンと伸びるコードでポーチにくっつけています。コードは100円ショップで買いました。
ドライバーとペンチはあまり使わないのですが持ち歩いています。たまに役に立ちます。
ピンセットは種まきなどの細かい作業で使う他に、固くなった鉢の土をほぐしたりするのに使います。刃先の曲がっているタイプが好きです。
カラビナを使ってぶら下げているのは、クレマチスの蔓を支柱に誘引するためのビニール被覆ワイヤーです。
以前は4ミリ幅のものだけしか使っていなかったのですが、あるとき二階堂ボスが間違えて細いものを買ってしまって、仕方なく使ってみたらクレマチスには意外と使いやすい事が判明。それ以来細いほうの被覆ワイヤーをメインに使っています。値段も安いし。
手袋は頻繁につけたり外したりするため、ぶらさげて持ち歩けるようにしています。
道具を入れているツールポーチはモンベルのものです。シンプルな形と丁度いい大きさで使いやすく、しかもとても丈夫に出来ています。
今使っているのがダメになったらまた同じのを買おうと思っているのですが、なかなかダメになりません。困ったものです。
写真で下に敷いている手ぬぐいは仕事中は頭に巻いています。夏は濡らして首に巻いたりもしています。
ちなみに、普段は普通の和柄の手ぬぐいなのですが、クレマチス園の公開期間中だけ、クレマチス柄の手ぬぐいに変えています。誰か気付いてたかな?
ページトップへ
- 11月22日(火) パンパスグラスの根は凄かった。
- 屋外栽培班の二階堂です。
大温室外周のひっそりした場所に、数年前からパンパスグラスが育ち始めました。
温帯中央の芝地で育てている株から種が飛んだのだと思います。
春からの除草もいい加減落ち着いたので、ようやく抜こうとしたところ、まったくびくともしない。
仕方なくバックホーで引っ張ったら、厚さ10㎝の根が2畳ほど広がっていました!
今後パンパスグラスの実生を見つけたら、とっとと抜こうと決めた秋晴れの日でした。
ページトップへ
- 11月18日(金) つくば蘭展 ~10年越し、もっと青いラン~
- こんにちは。登録室のTです。
「蘭展は毎年11月頃に開催されていたと思うのですが、今年はないのでしょうか?」とのお問い合わせが、続けて2件ありました。たしかに、過去5年間の開催時期は、2019年のほかは11月でしたので、「11月は蘭展の月」との印象が強いのかと思います。
次の蘭展は、2023年1月22日(日)~29日(日)までの8日間の開催となります。現在、チラシやポスター、そしてweb公開に向けて準備中です。
展示内容は、当園が誇る世界のめずらしい野生ランコレクション、愛好団体の皆様に出品いただく世界の美しいランの他、これまで当園で咲いた青い野生ランの写真展、さらには、世界初公開となる青いランなど盛りだくさん。
「世界初公開ですって?いやいや、青いランといえば、たしか2013年にも展示されましたよ!」という声が聞こえてきそうですが、実は今回公開予定の青いランは、あの時とは別品種なのです。最先端研究の10年越しの成果が結集された、新たな青いランとの出会いに乞うご期待!!
ページトップへ
- 11月14日(月) 腰道具シリーズ④ ★各栽培員が使っている腰道具類を不定期で紹介します★
- 圃場スタッフのよっしーです。
私の仕事は主に水草の栽培と水草栽培関連機材のメンテナンスです。
水草の栽培は水槽で管理する物が多く、使用する道具、機材の種類も豊富で、一度では語り尽せないため、ここではざっと全体像だけ紹介したいと思います。
まず初めに、道具入れとメインで使用している道具を3つ紹介します。
作業上機材のメンテナンスをするため、機材の部品や消耗品を収納できるよう、ポケットの数が多い物を採用しています。
左側より
①ピンセット(大)/根をほぐしたり、植替えの際、根本を整えるために使用します。
②トリミング(水草の長さを切りそろえる作業)用ハサミ/主に葉や茎の柔らかい水草のトリミングに使用しています。細身のハサミで、密植された水草の中でも、水草の間を縫って差し込む事ができ、ピンポイントで狙いを定め、カットすることができます。
持ち手の動きがスムーズで長時間の使用でもストレス無く使用できますが、やや堅めの茎や大きな水草をトリミングするにはややパワー不足です。
③ピンセット(小)/水草関連の作業するうえで、一番使用頻度の高い道具になります。水草を植えこんだり、肥料を土に差しこむ等の場面で使用します。
携帯している物が多い為、道具入れの中身については、次回より詳しく説明していきたいと思います。
ページトップへ
- 11月11日(金) キイレツチトリモチが今年も咲きました!
- 屋外栽培班の二階堂です。
キイレツチトリモチが土からモコモコ出てきて咲きました!
樹木に寄生する植物で、葉緑素がなく乳白色です。根も葉もよく分かりません。
土から掘り出して見たところ、根塊のような部分で樹木の根を取り込んでいました。
この度はトベラから水と光合成産物を奪っています。
がんばれトベラ!
キノコの傘にしか見えない部分に、小さい花が咲いています。
絶滅危惧植物温室で展示していますので、顔を近づけて確認できます。
ページトップへ
- 11月3日(木) ヤシの古葉切り
- 屋外栽培班の二階堂です。
毎週月曜休園日は温室高木剪定デー(2022年10月19日(水)ブログ参照)。
先日はサバンナ温室のオキナワシントンヤシの古葉切りを行いました。
葉の付け根部分が網状の茶色いスカートみたいに広がっているのが分かるでしょうか。この一見柔らかそうに見える繊維の集まりは、とても硬くてなかなか切れない。ヤシによっては幹をぐるりと囲い(2022年2月15日(火)ブログ参照)、タワシの材料になったりします。
ヤシの葉鞘を形作る植物繊維は、薄く広がると網状のマットになる性質なのかもしれません。ヤシの古葉切りはかなりの高所作業なのであまり気乗りしない仕事ですが、そんな場所でこそ見られる事柄があると、次の機会が待ち遠しくなってしまいますね。
ページトップへ
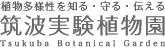
![]()







