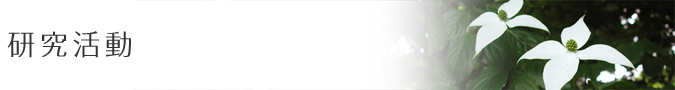- 筑波実験植物園の研究
- 分子系統解析と分類学の統合
- 絶滅危惧植物の進化と保全に関する研究
- 生物の相互関係が創る生物多様性の解明
- 生物多様性の解明に向けた生物多様性地形図の作成
生物多様性の解明に向けた生物多様性地形図の作成
生物多様性
生物多様性とは、生物には同じものが二つとないという性質のことで、社会性昆虫の研究で有名なウィルソン(E. O. Wilson)が最初に提唱した言葉です。遺伝子、形態、生態などいろいろな見方の生物多様性がありますが、ここではさまざまな種がいることに着目した種多様性として生物多様性をとらえます。
地球上には名前がついているものだけで150万種の生物が生息・生育することが知られ、そのうち30万種以上を植物が占めています。日本にはコケ、シダを含めると植物が7000種ほど生育します。日本の植物の多様性は中国ほどではないにしても、ヨーロッパ全域よりも高いといえます。
生物多様性ホットスポット(biodiversity hotspot)
生物は、食物網(食物連鎖)で代表されるように、互いにつながりあっています。ヒトは生物の1種でありながら、もっとも多くの生物をさまざまな用途に利用する生物であるといえます。したがって、生物多様性は私たちの生活を支える、なくてはならない基盤なのです。しかし、拡大する人類の社会活動が、その生物多様性を脅かし、そこに生息・生育していた生物の減少や滅失を招いているのを目の当たりにします。そんな中で自然保護の意識が高まり、自然環境保全の活動が活発になってきました。その一つが、生物多様性ホットスポットを設定して、そこに生息する生物を保全しようとする動きです。
生物多様性ホットスポットという言葉は、保全生物学者ノーマン・マイヤーズ(Norman Myers)によって1988年に提唱されました。ホットスポットは、その地域に維管束植物の固有種が1500種以上生育し、高い生物多様性を誇る一方で、自然植生が70%以上損なわれて破壊の危機に瀕している地域を指します。固有種がその地域から消失することは、地球上から完全にいなくなることを意味します。全地球的に生物多様性を保全するのは理想的ではあっても現実的ではないので、まず、固有種が集中し環境破壊が差し迫っている地域を保全して、絶滅する種の数をできるだけ減らすことが期待されているのです。固有種でなければ、他の地域に生息する集団が生き延びる可能性があるからです。
2000年に世界で25地域がホットスポットに認定され、その後いくつか追加修正があって、現在では34となっています。地球の地表面積のわずか2.3%でありながら、絶滅が危ぶまれる哺乳類、鳥類、両生類の75%の種が生息し、すべての維管束植物の50%と陸上脊椎動物の42%が34のホットスポットにのみ生育しているということです(コンサベーション・インターナショナル)。そして、日本もそのひとつに認定されました。

クマガイソウ(絶滅危惧II類)
固有種
日本産植物の多くは朝鮮半島、台湾、中国大陸などにも分布しますが、日本に特産する固有種は全体の約33%を占めます。このように、生物は形や生態ばかりでなく、分布域も種によって特徴があります。日本の固有種としては、オオシマザクラ、シラネアオイ、コウヤマキ、ブナなどがよく知られており、固有種の中でも、オゼソウ、キタダケトリカブト、ハヤチネウスユキソウ、ムニンノボタン、ヤエヤマヤシなどは狭い地域にしか生育せず、個体数も少ない希少種です。

シラネアオイ

ブナ
生物多様性地形図
日本のどこに植物の種が多いのか、固有植物が多いのか、絶滅危惧植物が集中しているのか、なぜそうなのか。国立科学博物館では、それを明らかにする第一段階として、生物多様性地形図を製作しました。これは、全生物の種類が多い地域、絶滅危惧生物が多い地域,あるいは固有種が多い地域など、国内の生物多様性ホットスポットを探り当てて、地形図のように表す試みです。
絶滅危惧生物の多様性地形図から、絶滅危惧種の多いピークが誰の目にもはっきりし、そのような絶滅危惧植物ホットスポットこそ保護区として保全されるべきであることが理解されるでしょう。また、固有種の多様性地形図ができれば、固有種がある地域に集中する原因を探る手がかりが得られ、それに系統関係も加味すれば、集中の歴史的側面が明らかになると期待されます。
なお、多様性地形図作成は開館130周年記念プロジェクト「生物多様性ホットスポットの特定と形成に関する研究」の成果で、現在、絶滅危惧植物の多様性地形図については研修展示館2Fで展示しています。