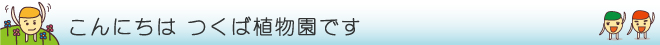
<<前年 | 翌年>>
<< 2009年10月 >>
- 10月30日(金) どんぐりで染物!その2
- 登録室のYです。
先日お伝えした、どんぐりの染物。
一体何を作っていたかというと…。
写真をごらん下さい。
布に浮かび上がる「どんぐりミュージアム」の文字がお分かり頂けますでしょうか?
これをつなぎ合わせて、ご来園の皆さまをお迎えする、のれんにするのです。
文字を染め抜くというのは、思いのほかに難しい作業でした。
輪ゴム、割りばし、アルミホイル、ボンド…様々なものを使って試した結果、どんぐりを輪ゴムでとめるという方法にたどり着きました。
下書きの文字に沿って、小さなどんぐりをひとつひとつとめていくという根気の要る作業でしたが、ボランティアの方々のご協力で、無事、完成。
輪ゴムでとめた部分のにじみ具合が絶妙な、味わい深い仕上がりとなりました。
この力作、「どんぐりミュージアム」で、ぜひごらん下さい!!
ページトップへ
- 10月28日(水) 歩道橋の横断幕・どんぐりミュージアム
- 事務のIです。
通常は専門の業者に依頼して作ってもらう横断幕ですが、
11月1日から始まります「どんぐりミュージアム」は
過去の企画展の横断幕を再利用しました。
最初に事務スタッフが白いペンキで古い文字を塗りつぶし、
その上からマルチアーティストのスタッフ永田くんが文字を
書いてくれました。
つくば市内の歩道橋3箇所に取付けてありますので、ご注目下さい。
ページトップへ
- 10月27日(火) 継続は力なり
- 國府方です。
多様性区でトウモロコシの原種と考えられている「テオシント」の実がつきました。
雌花の中を開いてみると確かにトウモロコシの粒に似たものが十数粒ほどあります。
かつて、食用トウモロコシは「テオシント」のように果実が小さく、少なかったと考えられています。
古の人々は、より果実が大きく、多い個体を選抜することを数千年にわたって繰り返し、私たちが食べるトウモロコシにたどりつきました。
古の人々の生物多様性の恵を活用した絶え間ない努力に感謝です。
ページトップへ
- 10月23日(金) どんぐりで染め物!
- 登録室のYです。
どんぐりで染め物が出来るのをご存知ですか?
今日はボランティアの皆さんと、どんぐり染めに挑戦しました。
来月開催される「どんぐりミュージアム」で展示する、あるものを作るのです。
まずたくさんのどんぐり(今日はコナラを使いました)を煮出します。
写真は、煮出した後のどんぐりと煮汁です。
なかなか渋くて素敵な色合いですよね!
この煮汁を使って、今度はさらしを染め上げていきます。
試行錯誤の結果、出来上がった作品は……次回のブログにてご紹介します!!
「どんぐりミュージアム」は11月1日から23日まで開催いたします。
皆さま、ぜひご来園ください!
ページトップへ
- 10月22日(木) 日本最大のどんぐり
- 堤です。
入手しました!日本最大として知られるオキナワウラジロガシのどんぐり。オキナワウラジロガシは琉球列島に分布する植物で、その巨大な板根はみたことありますが、巨大などんぐりの実物を見るのは初めて。
新聞切れ端上のシラカシのどんぐりと比べるとその差は歴然!これだけ大きいと見応えがあります。もちろん、来月からの「どんぐりミュージアム」で展示します!!
ページトップへ
- 10月21日(水) さて、これはなんでしょう?
- 育成管理の二階堂です。
11月1日から始まる「どんぐりミュージアム」にむけて、急ピッチで準備を進めています。
さて、写真にあるものは何を作っているかわかるでしょうか?一見鳥かごに見えなくもありませんが、実はこれ、どんぐりなんです。それも長さ2.5mと巨大などんぐりです。人目を引くようにとの目的もありますが、少しだけ工夫があって、小さな子供さんがちょっと遊べるようになっています。
さあ、開催まであと10日しかありませんが、これから紙を張って色塗りをして間に合うでしょうか!?
ページトップへ
- 10月20日(火) 日本で一カ所
- 陸上植物研究グループの海老原です。
先日の奥山研究員の報告にもある大分県調査の主目的は、日本では同県にしか分布が知られていない2種のシダ(いずれもホウライシダ属のオトメクジャクとホウライクジャク)でした。特にホウライクジャクはたった1ヵ所しか自生地が知られていない超稀産種で、いずれの産地も天然記念物に指定されています。
立ち会ってくださった教育委員会の方のお話では、最近保護地の崖が崩落し個体数が著しく減少してしまったとのこと。石灰岩の崖のような不安定な環境に生育する稀少種は、自生地を手厚く保護するだけで絶滅から救うことは難しいという現実を目の当たりにしました。
ページトップへ
- 10月17日(土) 巣!
- 続けて育成管理の二階堂です。
今年は例年に比べてハチの数が少ないと感じていたのですが、この季節になってようやく飛んでいる姿を頻繁に見かけるようになりまいた。
その姿を追いかけていくとありました。写真中央に見える茶色い塊、これはキイロスズメバチの巣です。場所は生垣の中で、直径40cmを超えた大物です!ちなみに防護服を着ているのは事務長です。ハチの巣除去には毎年必ず事務長が出動します。殺虫剤を一切使用しないで生け捕りにするのが得意です。
ページトップへ
- 10月15日(木) 続・台風一過
- 育成管理の二階堂です。
先週8日の台風から数日たち、ようやく園内の掃除や整備も一段落しました。やむを得ず休園にしてしまったことがウソのように、最近の天気は爽やかです。台風被害を忘れないために、被害状況の一部を紹介します。
写真にあるのは樹高15mの約50年生のスギです。地上から3m付近で折れてしまいました。この木の下には植栽されている植物が沢山あるので、伐採撤去には結構な手間が掛かりました。映ってはいませんが、じつはそのとなりで同じクラスのコナラが根返りを起こしていました。これがまた見事な係り木になっており、倒すのに一苦労でした。
結局園内全体では大小合わせて10本近くが倒されました。
それらの多くに腐朽があったり重心が傾いていたりしていて、健全木が倒されたわけではないのですが、台風の怖さを思い知らされました。
ページトップへ
- 10月12日(月) 菌類H2Oの北硫黄島調査5(完結編) 急遽撤退?!
- 細矢です。北硫黄島調査レポートの続きです。
天候が急変したため、急遽予定を1日早め、20日に撤収することに。波や潮の予想から20日の昼には海岸から船に荷物を運ぶことになりました。無人だった環境に配慮して、キャンプ生活で出たゴミ、水のペットボトル、うんこも含めて、すべてのゴミを持ち帰ります。
食べ物や水は減っていますが、採集品がありますから、荷物の体積は倍増です。苦労して荷造りをしたら、山あり谷ありの道をとぼとぼと海岸へ下りていきます。海岸付近で大雨となり、全員見事な濡れネズミに。
さて、いよいよ、荷物の運搬です。サーフィンができそうな高い波が押し寄せるなか、全員が上陸の時のようにロープに沿って一列に並び、荷物をボートまでリレーしていきます。ボートが母船に戻っている間に「ウェットスーツ着用」の号令がかかりました。みんなあわてて各自のスーツに足を通し、すぐ泳いでボートに乗れるように備えます。
その時でした。一人一人着々とスーツを着ているのに、どうしても私の左足が入らないのです。右足はすんなり、とはいえないまでも入れることができたのに、なぜ?!他の人はウェットスーツを腰まで着て、すでに一列に並んでボートを待っています。こうなると焦るばかりです。作業の監督をしていた人からは「海水で濡らしてみましたか」「強く引っ張ってください」とアドバイスがありますが、どうしても左足が入りません。
「手伝いましょうか」との声に汗だくになりながら、「お、お願いします」と変な位置でスーツに足を通したまま、ピョンピョンと歩いて行きました。次に監督が言った一言を私は一生忘れないでしょう。「ちょっと待って!それ、腕!」なんと、私は左足をウェットスーツの左腕に通そうとしていたのでした。みんな、一瞬の沈黙の後、吉本の喜劇みたいに大爆笑で崩れ落ちました。ピリピリとした緊張感が一瞬ほぐれた瞬間でした。
この事件は後に「北硫黄島探検のオチ」として知られるようになったとかならなかったとか・・・。
さて、以上のような山あり谷ありの行程で、私たちは100点以上の菌類と地衣類を採集しました。これらの解析はまだ始まったばかりですが、一部をご紹介しましょう。
北硫黄島には川はありません。一時的に雨の後にできる川はあっても、一年を通じて流れている川はないのです。ところが大雨の後、ベースキャンプの近くで、大雨の後の枯れ沢に水が流れていたのです。この川に水泡を発見。水泡には「水生不完全菌類」という菌類の胞子がトラップされていることが多いのです。北硫黄島の水泡を持ち帰って観察してみたところ、なんと、多数の水生不完全菌類の胞子が見つかりました。
これらの菌は絶え間なくもたらされる湿度を生かして、ふだんはわずかな水の中で生きているのでしょう。そして、雨などでできた川の流れにトラップされるのでしょう。でも、北硫黄島が出来た時は火山島で生物はいなかったはず。では、どこかから入ってきたのでしょうか。通常は水で胞子を散布するカビが実は飛ぶこともあるのでしょうか。興味は尽きません・・・。
北硫黄島は本当に不思議な島でした。
 |
ページトップへ
- 10月10日(土) チャルメルソウ調査は修験道?
- 奥山です。
10月5-7日の日程で、シダが専門の海老原研究員とタッグを組んで大分県に植物調査に行ってきました。
写真は調査の成就を願い精神統一をするためにまさに滝に打たれようとしているところ、、、ではなく、滝の間際に生えているツクシチャルメルソウの調査をしているところです。
チャルメルソウの仲間はどれも、滝のような水しぶきが常にかかる環境を好むため、私はしょっちゅうこんな場所で調査しています。
この種はただいま、絶滅危惧植物展で生きた株を展示中です。今の時期は花が咲いていないのであまりぱっとしない姿ですが、よかったら気にかけて見てやって下さい。
常に滝に打たれて暮らしている彼らこそ、「修験者」なのかもしれません。
ページトップへ
- 10月9日(金) 貴重な絶滅危惧植物
- 事務のIです。
可愛らしいピンクのマルヤマシュウカイドウは
絶滅危惧植物展の期間中しかみることができません。
透明感のある花びらは繊細な和菓子のようで、ちょっと
美味しそうにみえます。お腹がすいている方はお気を付け下さい。
最終日の12日(月・祝)まであと4日です!
ページトップへ
- 10月8日(木) 台風一過
- 育成管理の二階堂です。
台風18号、大暴れでした・・・。朝、恐る恐る園に来てみれば、多様性区では大きい木が1本幹折れ、1本根返りしていました。園路はすべて落葉落枝で覆われて、排水口は詰まってオーバーフローです。
9時を過ぎて雨は収まりましたが、まだ暴風圏にあったのでドングリや枝葉が一日中落ちつづけました。安全を確保してなんとか開園したいと思案翻弄したのですが、絶滅危惧植物展を開催中にもかかわらず、終日休園を余儀なくされてしまいました。
園が臨時休園したのはここ15年ではじめてのことだそうです。
ページトップへ
- 10月8日(木) 菌類H2Oの北硫黄島調査4 ロープで登山!山頂は別世界?!
- 細矢です。北硫黄島調査レポートの続きです。
山頂調査隊は、1泊2日の日程で、山頂を目指していきました。登山の専門家が前日に設置したロープを伝い、山頂への岩場を登るのです。重い荷物を担いだまま、命綱を頼りに進みます。
山頂は、霧で覆われていることが多く、雲霧林のようになっているそうです。コケの専門家は「別世界だった」といいます。
山頂隊が出発した日の夜、大雨が降りました。山頂付近は雷も近く、本当に怖かったそうです。もちろん、山麓側も大雨で、亜熱帯とは思えないような涼しい夜でした。
ページトップへ
- 10月7日(水) 菌類H2Oの北硫黄島調査3 いよいよ調査
- 細矢です。 北硫黄島調査レポートの続きです。
1日がかりでキャンプ地を整え、物資を運んだら、さあ、いよいよ調査です。ベースキャンプとなった精糖工場跡の周辺、ベースキャンプと海岸の間、ベースキャンプより上の地域・・・。それぞれの専門の分野の材料を採りに、ザックを担いで出発です。
私は土や腐朽した植物(カビの材料)、小型のきのこ類を採集しました。採集した材料は担当者それぞれの方法で、押して標本にしたり、シリカゲルで乾燥させたり(機械による熱乾燥ができないため)します。
夕方になるとベースキャンプには、オガサワラオオコオモリが現れ、ガジュマルやみかんの木の上にとまって葉っぱや実を食べたり、けんかしたり。毎日隊員たちはコウモリショーに見入っていました。
ページトップへ
- 10月6日(火) バナナその後
登録室のuです。
熱帯資源植物温室で8月初めに花を咲かせ始めたキングバナナの、今のようすです。
8月中旬にはまだ小さかった赤ちゃんバナナがしっかり大きく育っています。
苞につつまれた花序も、実のすぐ近くにあったのが、花を咲かせながら花茎を伸ばし、実から徐々に離れていっているのがわかります。
このバナナ、8月に2か所から花が咲き、1か月後にまた別の部分から咲きました。
ちょっとした開花ラッシュです。
ページトップへ
- 10月4日(日) 「絶滅危惧植物展」初日
- こんにちは。事務のシグロです。
昨日から企画展「絶滅危惧植物展」が始まりました。
皆さん、日本に自生する植物のどれ位が絶滅の危機に瀕しているかご存じですか?
私達の身近なキキョウも絶滅危惧植物です。
この企画展では、絶滅危惧植物についての現状、保全の大切さをパネル展示や展示案内で分かりやすく紹介します。稀少な生植物も展示しています。
この機会に足をお運びいただき、まず知ることから始めませんか?
ページトップへ
- 10月4日(日) どんぐりって楽しい!
- 育成管理の二階堂です。
9月26日のブログで宣伝をしました「どんぐりで遊ぼう」の試作を、植物園ボランティアのみなさんと行いました。鳥やネズミ、機関車やロケット、コマやヤジロベエ、それから綺麗なアクセサリーなどなど。これがどんぐりと枝だけで出来ているの?と言う作品が沢山できました!
写真中央付近にある雛のかごに使われているのはクヌギの殻斗です。どんぐりの様々な部位や、数種類のどんぐりを材料として用意する予定です。材料選びは種の違いを見つけることにつながるので、まさに植物園ならではのクラフトになると思います。
今回試作した作品は教育棟に展示してあります。どうぞじっくりと眺めてください。
ページトップへ
- 10月3日(土) キノコ観察会報告
- はじめまして、植物研究部の保坂です。きのこの研究をしています。
実は、先日のシルバーウィーク最後の日に、つくば植物園でキノコの観察会がありました。総勢25名の参加者といっしょに、植物園をくまなく歩き回りました。この時期を選んだのにはわけがあって、当然キノコがたくさん生えるはずだからです。実際、去年はちょうどこのくらいの時期に、それこそ足の踏み場もないくらいの数のキノコが生えていたのです!!!
ところが今年は晴天続き。まさに行楽日和のシルバーウィークでした。山登りを楽しむにはもってこいですが、キノコの観察には最悪と言ってもいい条件です。植物園を歩いても、カラカラに乾いた落ち葉を踏みしめる音ばかりが妙に気になります。
これでは今年の観察会は大失敗か...と心配したのですが、さすがに25人の目があると違います。最終的には20種を超えるキノコを観察することができました。採集されたキノコは乾燥標本となり、研究部の標本庫に大切に保管されています。
来年以降も植物園でのキノコ観察会は続ける予定です。来年こそは良い雨が降りますように。
ページトップへ
- 10月3日(土) あま〜い!
- 登録室のuです。
今、園内の橋のあたりや冷温帯区画で、砂糖をこがしたような香ばしくて甘い匂いがただよっています。
これはカツラの葉の香りです。落ち葉が発酵して香りを出します。
写真は冷温帯区の一角。カツラの葉のじゅうたんができて、甘い空気に満ち満ちています。
初夏のころから匂いはしているのですが、黄葉して葉が落ちるこの季節がいちばん強く香ります。
カツラは街路樹などにも使われているので、園内に限らず、わたあめみたいな匂いを感じたら、地面を見てみてください。黄色や茶色のハート型をした葉っぱが落ちているはずです。
すらりと高く伸びた幹や、黄色い葉をつけた枝の姿にもぜひ注目してください。
ページトップへ
- 10月2日(金) 花が咲いて、地面にもぐって、実ができました。
- 育成管理の二階堂です。
近頃、つくば市のあちこちで落花生が掘り起こされていますが、当園でも収穫の時期を迎えました。写真を御覧ください。どうでしょう、見事な殻が沢山ぶらさがっています!地面の中でどのように実が付いているのか想像できるように、教育棟内で吊るして展示をしています。どこからどのようにして実が成っているのか、どのように大きく成長するのかが良くわかると思います。
塩茹でして食べたい!と言う気持ちになるフレッシュな状態での展示は数日だけになります。ぜひ土日に足を運んでください。
ページトップへ
- 10月1日(木) ひみつ会議
- 事務の松本です。
今日は、どんぐりミュージアムの準備で、植物園ボランティアさん達とクラフトの試作会があるとのこと。
教えてもらった会場に到着!・・・まずは1枚パチリ。
みなさんの指先から次々にどんぐりを使った作品が生み出されていきます。
人の数だけアイディアがあって、見ていてとてもワクワクしました。
「どんぐりミュージアム」は11月1日から。着々と準備が進んでいます。
どんぐりクラフトは期間中の土日祝に体験できますので、お楽しみに!
ページトップへ
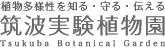
![]()





















