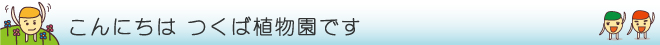
<<�O�N | ���N>>
<< 2009�N9�� >>
- 9��30���i���j�@�ۗ�H2O�̖k����������2�@�ܔM�n���̒��𐅂̉^���Ńo�e�o�e
- �ז�ł��B�k�������������|�[�g�̑����ł��B
���Ė����㗤��A���������x�[�X�L�����v�ɑI�̂͊C�݂��琔�L���A�W����190���̂Ƃ���ɂ��鐸���H��̐Ւn�ł��B�ł��A�����܂ōs���̂���ρB�Ȃ�Ƃ����Ă����ꂪ�Ȃ����߁A�������ĐH�������������ďオ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
�K���A�㗤���ɂ͕����o�Ă����̂ł����A�����̂���ɂȂ�Ɠ������͂���Ƃ�A�C�݂͂܂��ɎܔM�n���ŁA�d���ו���S���ł���Ƃ��ꂾ���ł�������̂悤�ɏo�Ă��܂��B�����o�e�o�e�ł��B�M�˕a�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�~�܂邽�тɐ������݂Ȃ���A�����ɕK�v�ȕ������グ�Ă����܂����B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��29���i�j�@���낻��Ő��ɍ����̔����Ԃ��炫�܂�
- �琬�Ǘ��̓�K���ł��B
���l����̎Œn�ɔ������[�v�ň͂������܂����B���̃G���A�ɂ͂Ȃ����Z���u�����Ԃ��炩���܂��B
�R�т̓�������̗ǂ��Ƃ���ɐ�����A���{�ŗL�̋ꖡ�������̖ł��B�����n�ł�30cm���炢�܂ŏ䂪�L�т܂����A�����̂��̂�5cm���x�Ə��^�ł��B�Ŋ���@�ł˂Ɋ����Ă���ꏊ�ɐ����邩�炾�Ǝv���܂��B���x�����ē��܂ꑱ���Ă��A���x�ł��L�тĖ��N�ڂ݂����邻�̍����͂������ł��ˁB
�O���ȍ��̔������ȉԁA10��������J���n�߂܂��̂ŁA�����̍ۂ͑����ɒ��ӂ��Ă����ɂȂ��Ă��������B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��28���i���j�@�ۗ�H2O�̖k����������1�@�㗤���K���H�I
- �͂��߂܂��āB�A���������̍ז�ł��B
�ۗށE���ތ����O���[�v�̋ۗނƒn�ߗނ̒S���ҁi�ז�E�ۍ�E�呺�ŁA���������Ƃ��Ēʏ�"H2O"�j��6���̌㔼�A���}���̂���ɓ�ɂ���k�������Œ������s�Ȃ��܂����B����́A��s��w�����ƍL����w�̍��������ɎQ���������̂ł��B
�������Ƃ����Ɖf��u����������̎莆�v�ɏo�Ă��铇�̂��Ƃ��Ǝv���l������Ǝv���܂����A�ł�����͒��������̂��ƂŁA���̑��ɖk�������Ɠ연�����̂R������ΎR�i�����j���\������Ă��܂��B����s�����k�������͒��������̖k70�L���̂Ƃ���A���}���̒��S�n�ł��镃������͓�ɖ�200�L���̂Ƃ���ł��B
�k�������ɂ͖�������ɈڐA�҂�����܂������A��O�̋����a�J�ȗ��A���l���ƂȂ��Ă���̂ł��B���̏㕔�ɂ͏�ɉ_��������A�R���͂����Ζ��ɕ����Ă����Ԃ̂悤�ł��B���n����ďo�����̂ł͂Ȃ��A�C��ΎR�����N���Ăł�����C�̌Ǔ��ŁA���������������A����ȏꏊ�ɂ͂ǂ�ȋۗނ�����̂ł��傤�B�������́A�����ŃL�����v�����𑗂�Ȃ���A�ǂ�ȋۗށi���̂��E�J�r�j�A�n�ߗނ����邩�A�������܂����B
���̗l�q�͗���12��20���̃f�B�X�J�o���[�E�g�[�N�ł��͂����܂����A����ɐ旧���A���ꂩ�牽�ɕ����ă_�C�W�F�X�g�������肵�܂��B
���āA�k�������͖��l���ƂȂ��Ă��璷�����߁A�D������V��������܂���B�������A���̎��͂ɂ͍��l���Ȃ����߁A�D���ڊ݂ł��܂���B
����A�ǂ����邩���āH
�Ȃ�ƁA�Ō�́A�j���ŏ㗤�ł��B�g�������A���ɑł�������\�������邽�߁A�E�F�b�g�X�[�c�E�����߂��ˁE�V���m�[�P�������A������Ȃ��悤�ɍŏ��Ƀ_�C�o�[���C�݂ƊC�Ƃ̊ԂɃ��[�v���Œ肵�܂��B�k�������܂ŗ���̂ɏ�������D���玊�߂܂Ń{�[�g�ōs���āA�_�C�u�I
���[�v��`���ĊC�݂ɏ㗤������́A���������[�v�ɉ����Ĉ��ɂȂ�сA�H���E���E��������Ȃǂ��o�P�c�����[�ʼn^�����܂��B�K���A�㗤���͔g���قƂ�ǂȂ���Ԃł����̂ŁA�傫�ȐS�z�͂���܂���ł����B
�������Ď������́A6��16���A�����㗤���ʂ����܂����B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��26���i�y�j�@�}�̃X���C�X
- �琬�Ǘ��̓�K���ł��B
�@11��1������23���ɂ����āu�ǂ�~���[�W�A���v���s���܂��B���̓y���̑̌��C�x���g�ɁA�ǂ��R�i���̎}���g�����N���t�g���[�N�u�ǂ�ŗV�ڂ��v����撆�ł��B
�ʐ^�ɂ���̂͂��̍ޗ��ɂȂ�R�i���̎}�������X���C�X�������̂ł��B�ǂ��ł��傤�A���Ă��邾���ł�����������肽���Ȃ��Ă��܂��H
�߁X�A�A�����{�����e�B�A����B�Ǝ�����s���܂��B�o���オ������i�͌�����̃u���O���ŏЉ�����Ǝv���܂��B���āA�ǂ�Ȃ��̂��ł���ł��傤���I
�y�[�W�g�b�v��
- 9��25���i���j�@�������A���s�ɍs����
- �����̂h�ł��B
�Ȃ�ƂȂ����s�̕��͋C���Y���Ă��܂��H
�����́u�����܂�v�̎ʐ^�ł��B
���̎��G�͖��N�q�K���o�i�����ꂢ�ɍ炫�A�u�����܂�v�̂������܂����Ȃ�ƂȂ����s�ɍs�����C���ɂ����Ă���܂��B
����������ɂȂ�ƍg�t�����ꂢ�ŁA�v�X���s�C�������܂�܂��B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��23���i���j�@�R�b�g���{�[�����e���܂����I
- �����Ĉ琬�Ǘ��̓�K���ł��B
���l����ō͔|���Ă��郏�^�̎����e���܂����B
�ꎞ�A���^�m���C�K�̔�Q������܂������A�����ɗ��h�Ȏ�����R���܂����B�܂��������J���Ă��܂��A�t���t���̃R�b�g���{�[���������ɂȂ�܂��B�ʐ^�������E���ɂ́A�J���O�̗̎��������܂��B
���̂܂����Ɏ��n�ł���A�ȑł��⎅�a���̍u�����J�����\��ł��B�܂������͖���ł��̂ŁA�����̂������HP�̃g�s�b�N�X��C�x���g�������܂Ƀ`�F�b�N���Ă��������B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��22���i�j�@���̉��ȉԂ͉��̉ԁH
- �琬�Ǘ��̓�K���ł��B
�L�c�l�m�}�S�A�n�L�_���M�N�B���i���������G���ƌĂԂ��Ƃ̑����A�����e�n�ō炢�Ă��鏬�����ԒB�E�E�E�B�I�V�����Ȕ��ɂ���ĉ��炵���f�R���[�g���Ă݂܂����I���瓏�ɂ���x�e�e�[�u���ɏ����Ă���܂��̂ŁA�����̍ۂ͂ЂƖڂ����ɂȂ��Ă��������B�@
���ʂ͎����ɂȂ�܂����A���������I�ɂ��̂悤�ȐA���B���A��������炵�ďЉ�Ă��������Ǝv���܂��B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��20���i���j�@����i���N�W
- �͂��߂܂��āA�����������̒��J��ł��B
���͐A�����̕~�n�̒��ɂ͐����̓����̌����҂��Ζ����Ă���̂ł��B
�������C�̖��Ғœ����i�w���̂Ȃ������j�����ł��B
�������Ă���̂��́A�܂�������@�����܂�����B
�Ƃ���ŁA�����Â��b�ɂȂ�܂����A3�N�قǑO�ɐA�����̂�����Ύs�̗ג��A�y�Y�s�ŁA���[���b�p���Y�̋���i���N�W�A
�}�_���R�E���i���N�W���蒅�E�ɐB���Ă��邱�Ƃ����R�������A
1�N�قǑO�̉Ȕ��̃����}�K�ŏЉ���Ă������������Ƃ�����܂����B
���̎��̋L���́A�摜�ƂƂ��ɉȔ��̃T�[�o�[�ɃA�[�J�C�u������Ă��āA�u�}�_���R�E���i���N�W�v�Ō������邱�Ƃ��ł��܂��B
����������ɂȂ������q����A�����悤�ȃi���N�W��߂܂����A�Ƃ������A�������������܂����B
�ꏊ�͉��Ƃ��Ύs�B�����J�ɐA�����܂Ŏ�����͂��Ă��������܂������A����ς�ԈႢ�Ȃ��}�_���R�E���i���N�W�ł����B
����܂ŁA���{�����Ŗ{�킪�m�F����Ă���̂́A�y�Y�s��2�����ƁA����̂��Ύs�݂̂ł��B�����n��ł����A���ꂼ��̒n�_�͐��L��������Ă��܂��B
�ǂ���������Ă��āA�Ȃ����̂悤�ȕ��z�����Ă���̂ł��傤�B
���́A�z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă������A�����A�����������ɂ�ł��܂��B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��19���i�y�j�@�n�x�i���A�E���h�D�[�T�J��
- �o�^���̒J�ł��B
�����́w�����̌�����A���x�̑�2�ʁe�n�x�i���A�E���h�D�[�T�f�̎�ޕ��i�ł��B
�����Ɍ�����j���������͔̍|�S���҂ł��B�ǂ�ȋL���ɂȂ�̂��y���݂ł��B
��ʍ��ɔ������R���Ƃ������̂��e�n�x�i���A�E���h�D�[�T�f�ł��B
�悭���������͐A�����̃g�b�v�y�[�W�ł��y���݂��������B
���̉ԁA�}�g�����A���������{���I�I�J�Ԃɐ��������܂����B
���{���ł����ł��������܂���B
���ɗ��Ă��������B
���҂����Ă܂��B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��17���i�j�@����������
- �o�^����u�ł��B
�R�n�����i��n���j�ɁA�t���b�V���ȗΐF�̍L�����p������܂��B
���̗ΐF�̓N�T�\�e�c�B���z�̂��ƁA�̂т̂тƗt��点�Ă��āA�ƂĂ���������������܂��B
�N�T�\�e�c�̓V�_�̂ЂƂŁA�t�̎R�u�����݁v�����̐A���̎�肾�ƕ����A�u�����A�m���Ă�v�Ƃ������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�t���ς͂Q�̃^�C�v������܂��B
�傫�����ׂ������t���h�{�t�i�ʐ^���E�j�A���^�ł�◧�̓I�Ȃ̂��E�q�t�i�ʐ^�����j�ł��B
�V�_�����̏��{�搶�ɂ��ƁA�E�q�t�����傤�Ǐo�͂��߂āA������������Ă���Ƃ��낾�����ł��B
���̎����ɏ����A�����A�����Ȃǂ̋}���Ȋ��ω����N����ƁA���̉e���ł����Ƃ����E�q���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A������ƂĂ��厖�Ȏ��ȂA�Ƃ̂��ƁB
�u�����I�v�Ɛ������������Ȃ�܂����B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��16���i���j�@����͊��H�����A�Ⴂ�܂��B
- �琬�Ǘ��̓�K���ł��B
�ʐ^���������Ă��������B�ג����Ȃɂ�������̂�������ł��傤���B�j�����j�������Ă�����̂ł��B�����A�w�r�ł��I�I�I�r�����ɂȂ��Ă������b�R�E�o����������������ę��肵�Ă���ƁA���܂��ɐ��Ƃ��Ă��銲�ɂȂɂ������ݕt���Ă��܂����B��u�A���H�Ǝv�����r�[�A��փV���[���Ɠo���Ă������̂ł��I�I���킟�����[���I�����ăw�r�Ɩڂ������āA���Ⴀ�����[�I
�����������͉��R�搶�ɘA���ł��B���ƌ����w�r�����Ă�������Ƃ���V�}�w�r�Ƃ̓����ł����B�ł͂Ȃ����Ǚ��ނ����ł��B���������Ȃ���A���R�搶�͑f��Ŋy�������ɕ߂炦�ɂ�����܂����B�w�r�͖����Η����Ƃ���ɒ�R���A�^�C���A�b�v�ʼn��R�搶�̕����ł����B���̌�c���ꂽ���́A��������ԂŖ�h�炵����_�œ˂����肵�A�w�r�ɂ�����ƂÂړ����Ă�����ĂȂ�Ƃ�������I���܂����B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��15���i�j�@�A���o�C�g�i�c�̐����K��D �`�A�����̊C�l�`
- ����ɂ��́I
���͐��\���ɂ��ז������Ă��������܂����I
�ړI�́w�R�A�}���ƃE�~�W�O�T�A�����E�L���E�X�K��(�g�ɂ���炵�Ă��Ă��킢��)���̏W����x���Ƃł��B
�ό��̕��������C�����i���Ă���̂����ڂɁA�������j2�l�̓E�F�b�g�X�[�c�ɃV���m�[�P���A����ɍ̏W�����A��������ԑ�(����l�b�g�ɂЂ�����������)��������Ԃ炳���A
�������ɂ����̂���Ȋi�D�ōŏ����̉�b���������A�Ԃ��Ԃ��ƊC�ɒ���ł����܂��B
�_�C�r���O�ł��Ȃ��̂ɃE�F�b�g�X�[�c�͂����������Ǝv���邩������܂��A
4-5���Ԃ����ƕ����сA���܂蓮���Ȃ��̂ŁA���̑����łȂ��ƈӊO�Ƒ̉����D���܂��B
�����Ĕw�������͑��z�ɂ��炳��Ă��邽�߁A��X�Ƃ�ł��Ȃ��I�Z���̃R�}�̂悤�ȑ̂ɂȂ�A�ɂ݂������܂��B
�������ő�ɂȂ�Ɛ��[��10cm���炢�ɂȂ��Ă��܂��A�炾�����ɂ��ă��]���]���Ă���������l�Ɍ����܂��B
����Ȃӂ��ɖ����ɂȂ��ĕ����Ă���Ƒ����������T�搶�������l�Ɋ������� �݂��
2m�������Ă���Ǝv����(���ۂ�1m���炢)�ł������E�c�{(�����n�i�r���E�c�{)�������݂Ă��܂����I
�������̂ŗ����オ��s����ȑ�����ڂ���ڂ�����Ƒ��蓦���܂����B
�����ƕ�����ł�����₾�Ǝv������Ȃ��́H��T�搶�͂��������܂����B
�����āA�E�c�{�͊�t�߂ɂ��Ăق����Ǝv���܂����B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��13���i���j�@�}���R�[�i�[
- �����̂h�ł��B
�A�����ɂ͂��q�l������̌����u���瓏�v�̒��ɐ}���R�[�i�[������܂��B
���̂��C�ɓ���́u��̑��Ȃ܂��m�[�g�v�Ȃǂ̃m�[�g�V���[�Y�ł��B
�C���X�g�����ꂢ�ōׂ����A���ɂ��ďڂ���������Ă���܂��B
���ꂩ��̋G�߂́u���̂����m����v���������߂ł��B
�ڂ����}�ӂ�A���厫�T�Ȃǂ��܂߂P�O�O���قlj{���ł��܂��̂ŁA���w�̑O��ɂ��傱���Ɖ{���A���R�����̂��߂ɏڂ������ׂ�Ȃǂ��ЁA�����p�������B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��11���i���j�@�炢����[�I
- �c���ł��B
�쐶��Ŏ�̃R�V�K���z�V�N�T�̖쐶���A��ڎw���ĕۑS�������s���Ă��܂������A���Ɍ��n�ʼnԂ��炫�܂����B��T�����琅�ʂ��������āA���ʂ���Ԃ���������܂����B�悭�ł������̂ŁA�Ԍs���L�тĂ��Ԃ͊J�����A����ɏo���Ƃ���ɊJ�Ԃ��܂��B
�܂��Ƃɂ����A�܂�����O�i�ł��B
�A�����ł��炢�Ă���̂������ɂȂ�܂��B���ڂɂ݂�ƒn���ł����A�悭����ƂƂĂ����킢���ł��B
��ʂ̕���������̂͐��E�ł��������Ȃ̂ŁA���Ђ��̋@��ɂ������������B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��11���i���j�@�܂��邢���K
- �琬�Ǘ��̓�K���ł��B
�ʐ^���������Ă��������B�ۂ����K������̂�������ł��傤���B�тō�Ƃ��Ă��鎞�ɁA�l�Y�~�炵�������������Ă����Ƌ߂Â��܂����B����Ɣނ͔w�������ďk���܂�A�҂����Ɠ����Ȃ��Ȃ�܂����A������B��������ł��B����͒K�Q����Ȃ̂ł��傤���B���ɂ͓�������ĔY��ł���悤�ɂ������܂����B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��10���i�j�@�u�����̒���12��36��������v�u�����ł��v
- �c���ł��B
�C�̐������������Ă���҂ɂƂ��Ă͔����Ēʂ邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u�Ă̑咪in���\�v
������A�����^�J�[������ŋL�����Ă���ƓX������Ɂu�E�~�V���E�u����Ă�c������ł���ˁv�Ɩ���A�����̊J��������˔@���������ʕNJ��ɓ˂����Ƃ��ꂽ�C���̏W�L���̂P�F�����͂₪�Ė����ɂȂ�҂ł��B
�A���̏W�̂Ƃ��ɒ����ӎ�����l�͂܂����܂��A�C�̐A�����̏W����Ƃ��ɂ͖{���ɕK���ł��B�ł����������咪�̊������ԑO��5���Ԃ��炢�������ł��̊Ԃ͐�����ςȂ��B�P���ɐ��[���������T���₷�����ƂƁA�Ԃ��ړI�̍���͊������ɍ炭�\�����������߂ł��B���̃��J�j�Y���͂悭�킩���Ă��܂��A�����Ŏ����邽�߂ɐ��[���������Ǝ̊m�������܂邱�Ƃ͊m���ł��傤�B
����1���ڌ����炸�A2���ڂ͂��F��������Ƃ���Y�Ԃ���������܂����B�ǂ���T���ׂ����A�ǂ�ȕ��ɋF��ׂ�����T�d�ɍl���čŏI���ɖ]�݂܂����B�i�Â��j
�y�[�W�g�b�v��
- 9��8���i�j�@���������u�n�ߗށv
- �͂��߂܂��āD�A���������̑呺�ł��D
���������u�n�ߗށv�̌��������Ă��܂��D
�n�ߗނ��ĉ��H�R�P�H�Ǝv���������������邩������܂���D
���́C�n�ߗނ͋ۗނ����ނƋ������đ̂�����Ă��镡�������Ȃ̂ł��D
���E�ɂ͓����Ă���̂ɔF������邱�Ƃ̏��Ȃ��n���Ȓn�ߗނł����C���݂�������ƐF�X�Ȏ�ނ��g�߂Ȋ��ɐ��炵�Ă��邱�ƂɋC�����悤�ɂȂ�Ǝv���܂��D
����Љ��̂́u���W�S�P�v�ł��D
������Graphis�ƌ����܂��D���̖��̒ʂ蕶����������Ă���悤�Ɍ����܂����C���̕����ł͋ۗނ̖E�q������Ă��܂��D�D���F�����̒n�ߑ̂ɂ̓X�~�����Ƃ������ނ��������Ă��܂��D
���ꂩ��������Ɍ������\�I�Ȓn�ߗނ��Љ�Ă����܂��I���y���݂ɁI
�y�[�W�g�b�v��
- 9��7���i���j�@�C���h�ɍs���Ă��܂���
- ��ł��D
�o���ŃC���h�ɍs���Ă��܂����D
�ʐ^�͊X�H���̊��̈ꕔ�ŁD�n�J�}�E���{�V�̒��ԁC�V�V�����̒��ԁC�q�g�c�o�̒��Ԃ��Ƃ��닷���Ƃ������Ă��܂��D�M�тł͂��̂悤�ɊX�H���ɒ����A��������������Ă���l�q�������܂��D
�s��̃A�b�T���B�쐼���́C�O���l���قƂ�ǂ��Ƃ���Ȃ��n��炵���C�Ԃ��~��ĊX�H�����ώ@���Ă���ƁC���̂܂ɂ����\�l�̑��l�ɂނ炪���A���������ώ@����Ă��܂����E�E�E�B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��6���i���j�@�G���͍ޗ��ł�
- �琬�Ǘ��̓�K���ł��B
�ʐ^�E��O�Ɍ�����̎R�́A�����ŏ������������W�߂����̂ł��B����ɐ��������Ղ�^����2�T�Ԃ�����ƁA�ʐ^�����Ɍ�����R�̂悤�ɍ����Ȃ�܂��B
�o�b�N�z�[�Ő�Ԃ����s���Ă���Œ��̂��̂ł����A�������̗͂Ŕ��y���A������͓��C�����E���E�Əo�Ă��܂����B���̌㐔���������đ͔�ƂȂ������͉̂����̂��������ŗ��p����܂��B
���ꂩ��͗��t����ʂɏo��G�߂ł��B���x�͕��t�y��肪�n�܂�܂��B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��5���i�y�j�@����Ȃɑ傫���炿�܂����I
- ���R�ł��B
�W���P�R���ɂ��Љ���A�A�I�X�W�A�Q�n�̗��ł����A�����ɂ����܂ő傫���Ȃ�܂����B
�W���P�R���̎��ƌ���ׂĂ݂Ă��������B�����I�ߗc���ł��̂ŁA�߁X匂ɂȂ�ł��傤�B
���̃A�I�X�W�A�Q�n�A�����Y�݂����Ă����O���Y��Cinnamomum parthenoxylon�i�V�i���}���E�p�[�e�m�L�V�����j�̗t����100%�ň�Ă܂����B
����ŁA���̃`���E�����̐A����H�ׂĂ�����ƈ���Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��ؖ�����܂����ˁB
�����₩�ł����A�V���������ł��B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��4���i���j�@��������
- ����ɂ��́B�����̏��{�ł��B
�������u���������v�ŁA���̕ς����������Ă��܂��B�H�ł��ˁB
��ƒ��ɁA�J���t���[�W�����̂�����ɑ������܂����B
�������I
�����͐A������������܂����A�����������ł��B
���̊ԂɁA�̏�ɁA���̑��v�������Ȃ��ꏊ�ɐ���ł��܂��I
�y�[�W�g�b�v��
- 9��3���i�j�@�ނ����̐A�����i�N���V�b�N�J�[�j
- ������I�ł��B
�}�g�����A�����͍�N�J��25���N���}���܂������A
�J�������͘A�������̂��q���܂�������������A
���ɓy���͎Ԃ��s�������Ă��������ł��B
���݂�Ƃ܂�ŃN���V�b�N�J�[�̃p���[�h�̂悤�ł��B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��2���i���j�@�����S�i����3�y���{�뉀�z
- ����ɂ��́B�����̏��{�ł��B
�F�l�A�����œ�����t�����܂��܂�����A���̂܂܉��̕��ւ������݂��������B
��������̏o�����J���܂��ƁA�����ɂ͓��{�뉀���I
�����́A�u�������x���鑽�l����v�̈��A���{�뉀�̐A���R�[�i�[�ł��B
�Ԃ��P�̉��ł��c�q��H�ׂ����E�E�E
�ƁA�ʂ邽�тɎv���܂��B
�y�[�W�g�b�v��
- 9��1���i�j�@���l���n�`�}�A���R���A�����֏o���ł�
- �琬�Ǘ��̓�K���ł��B
�ʐ^�ɂ���̂́A���{�Ő�ł̊�@�ɕm�����A���̕��z���x���R�̍����ŕ\���������l���n�`�}�ł��B���É��̓��R���A������9���ɐ�Ŋ뜜�A���̓W��������A�o�����邱�ƂɂȂ�܂����B
�����̎��̎d���͑�H�d���ł��B�n�`�}�̃T�C�Y�͏c��150cm�A����40cm�A�d����50kg���x�ł��傤���A������^���̍ۂɕی삷��ؔ��̍쐬�ł��B12mm�̃R���p�l6���A4m�̃^����8�{�g���܂����B�����̂������Ȃ苭�łȂ��̂��o�����̂ł����A���ꎩ�̂���70kg�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���g�����d���E�E�E�B
�n�`�}�͂܂������ɋA���Ă��܂��B���̍ۂ͂��ЂƂ���x�����ɂȂ��ĉ������B
�y�[�W�g�b�v��
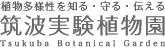
![]()






















