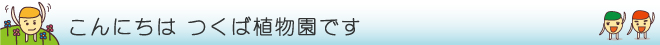
<<前年 | 翌年>>
<< 2010年1月 >>
- 1月31日(日) シナマンサクが咲きました
- 登録室のuです。こんにちは。
サバンナ温室の手前で、シナマンサクの花が咲き始めました。
リボンがカールしたような花びら、くっきりした黄色と赤の組み合わせが印象的です。
顔を近づけるとこの花特有のいい香り!
みかんの匂いに似ている、と感じるのは私だけでしょうか?
駐車場ではハマメリス・ベルナリスが咲いています。
こちらは北アメリカのマンサクです。
2月に入ると日本のマンサクが、さらにそのあとからマルバマンサクが咲き出します。
園内にある、早春に咲くマンサクの中でいちばん早く咲くのがシナマンサク。
「まず咲く」がなまってマンサクになったという語源の一説からすると、シナマンサクはマンサクの中のマンサクと言えそうです。
ページトップへ
- 1月26日(火) モズの忘れ物
- 育成管理の二階堂です。
ドウダンツツジの枝整理をしていたら、モズのはやにえを発見。めずらしいものを見つけたうれしさをこのブログで伝えたかったのですが、この写真を見たら寂しい気持ちになってきました。
さて、背景に溶け込んでしまっている中央の生き物、なんだか分かりますか?
ページトップへ
- 1月25日(月) おめん
- こんにちは。事務の松本です。
もうすぐ節分・・・にちなんで、植物園ではおめんづくりを体験できます!
おめんのベースは、ホオノキという木の葉です。
とっても大きい!
おめん作り体験は、23日・24日の10時から15時までです。
人気次第では2月も継続します。
早春の花も咲き出した今週末、ぜひ遊びにきてください♪
ページトップへ
- 1月24日(日) アサザのおくるみ
- 育成管理の二階堂です。
昨年の年末に掘りあげた湿地のアサザ、年を越えたら根についていた泥が流されたらしく、水面に浮遊しているのを発見・・・。あわてて根に赤玉を抱かせてネットで包みました。これから新芽が出る箇所を締め付けないように、やさしく、でも崩れないようにしっかりと、まるで「おくるみ」です。
どこかに出荷できそうな仕上がりに、おもわず写真をとってしまいました。
ページトップへ
- 1月22日(金) シモバシラ
- (前のブログからの続きです)
でも今日は植物のシモバシラです。
「シソ科のシモバシラは小さな花をたくさん付けるけど今の時期じゃないでしょう!」
その通り!!
花ではなく枯れた根本に注目!!
大寒のこの時期の現象 ☆:★ シモバシラ ★:☆
週末はまた寒くなりそうです。
早めにお出かけしてみませんか。。。
以下説明です。
☆●☆◆☆▲☆■☆▼☆
地上部が枯れても生きている根は水を吸い上げます。それが茎から染み出し凍る事によって霜柱(シモバシラ)が作られます。当園では、シソ科のシモバシラやキク科のイガアザミなどに初冬の午前10時頃まで見られる事があります。茎が破れたり地中の水が凍る頃になると見られなくなります。(2008年1月 今週のトピックスより)
ページトップへ
- 1月22日(金) 霜柱
- 植物園の谷です。
皆さんはシモバシラと聞くと土の中の霜柱を想像されますね。
「家の庭にもある。。」と云う霜柱はこちら。
植物園にも至る所に出現しています。
見ているだけで寒くなりますネ、、、
霜柱を見たことが無いと言う方いらしてください。
まだまだ見られますから。。。。
ページトップへ
- 1月18日(月) サソリに見えますか?
- 植物園の谷です。
既に先日の記事でも紹介されていますが、今日はあらためてこの珍しいランを紹介します。
学名がアラクニス・ロンギセパラ(Arachnis longisepala)
その名を「サソリラン」と言います。
恐ろしい名前とは裏腹に何とも華奢な花をたくさんつけています。
赤茶色の長いところをシッポに見立てます。
サソリっぽく見えるかどうか!?
確認にいらして下さい。
この他に、熱帯資源温室にはかつて東京ドームのラン展で日本大賞に輝いたラン、
水生温室では世界一大きなランがそれぞれ皆様をお待ちしています。
ページトップへ
- 1月16日(土) マダガスカルの女王
- 事務のIです。
熱帯資源植物温室で見事に咲き誇る「マダガスカルの女王」。
鮮やかなピンク色の花に、目も心も奪われます。
そしてもう一つオススメの…(次のブログへ続きます)
ページトップへ
- 1月16日(土) サソリラン
- そしてもう一つオススメの「サソリラン」。
花弁、がく片が長く伸びる様子が「サソリ」に形が似ているということで、このようなニックネームがつけられています。いくつものサソリが枝にぶら下がっているように見えますよ。
こちらは熱帯雨林温室・低地林1階でみられます。
ページトップへ
- 1月15日(金) 他人の空似?オーストラリアの「マムシグサ」
- 奥山です。
年が明けてから寒い日々が続いていますが、もちろん当園の温室は『常夏』です!バケツランの見頃は過ぎてしまいましたが、他にも次々と奇妙なランが咲いています。
今回はその中から、オーストラリア原産のとびきり変わったラン、プテロスティリス・オフィオグロッサ(Pterostylis ophioglossa)を紹介します。
プテロスティリスの仲間はオーストラリア、ニュージーランド、ニューカレドニアからパプアニューギニアに100種あまりが分布しており、どれも小さなハエの仲間(キノコバエなど)が花粉を媒介すると考えられています。直接本種の観察例がある訳ではありませんが、非常に姿のよく似たプテロスティリス・アロビュラ(P. alobula)で花粉が運ばれる様子の詳しい観察例があります。
おそらく特殊な匂いによっておびき寄せられたキノコバエの仲間は、がくに包まれて出来た空間に閉じ込められます。キノコバエは光をたよりに外に脱出しようとしますが、そこはしたたかな花です。がく(上がく片)に透明な部分(白い筋)があって光が内部に集まるため、花の奥は明るいのです。こうしてキノコバエはまんまと花の「ねらい通り」のルートを通って脱出せざるを得なくなり、体に花粉がついてしまいます。
それにしてもこの花、サイズこそ小さいですが、びっくりするくらいマムシグサの仲間の花に似ています。マムシグサはランとは全く類縁の遠いサトイモ科ですが、何と、同様の花粉媒介の仕組みを持っていることが知られています。このように、同じ目的を達成するために、異なる生物が別個に、非常に似た姿を進化させることを、平行進化、あるいは収斂(しゅうれん)進化とよんでいます。
開花中のプテロスティリスは熱帯雨林温室・山地林の2階で展示しています。
ページトップへ
- 1月14日(木) 2010年初園内整備
- 植物園の谷です。
毎月行っている園内整備です。
今日が今年の初作業です。
園長、事務長、研究員から非常勤まで総出の作業となりました。
ご来園頂いた皆様にはお馴染みの教育棟(正面入り口)。
その床磨き中です。
ゴシゴシ、ゴシゴシ、、、
激落ちスポンジを使って一つ一つタイルを磨いています。
寒中と云うのに皆「暑い暑い」を連発!
丸2時間ゴシゴシ、ゴシゴシ、心を込めて磨きました。
広い教育棟の半分が終了しました。
結果は一目瞭然!!
次のご来園の際には床にもご注目下さい。☆.・.・.・.☆
来月には床全体が綺麗になる事でしょう。
ページトップへ
- 1月11日(月) バケツラン開花しました!
- またまた事務のIです。
バケツランが開花しました!
ダーウィンが受粉の仕組みを研究したことで有名な植物です。
花弁の1枚がバケツの形になっているため、バケツランと呼ばれます。
見ごろは1月14日(木)頃まで、熱帯雨林温室・山地林の2階で展示しています。
お待ちしております!
ページトップへ
- 1月10日(日) 植物のつくり
- 続けて事務のIです。
同じく研修展示館1階に「植物のつくり」という大きな模型があります。
手前のボタンをポチっと押してみてください。
根・葉・茎について、音声で分かりやすく説明します。
屋外を見学するにはちょっと寒いかな?という時には、研修展示館の展示をじっくりご覧下さい。
ページトップへ
- 1月9日(土) 県の木
- 事務のIです。
研修展示館の1階に、木で出来た大きい日本地図があります。
茨城県は梅の木、東京都はイチョウの木という様に、各都道府県の木として選ばれた木の材をもとに作成しています。
ぜひ、質の違うそれぞれの材に直接触れて楽しんでください。
ページトップへ
- 1月4日(月) そんな願いとはうらはらに
仕事初めに植物研究部で行っている研究プロジェクトの担当箇所の原稿を見直したところ、こんなにたくさんの付箋をはるはめになりました。原稿全部に目を通し、問題がある箇所に付箋をはってメモしていたら、これだけの数になってしまったのです。
これらの問題を一つ一つ文献や標本をもとに全て調べ直さねばならぬのかと思うと、、、お正月気分もすっかり冷めました。今年も怒濤の一年となりそうです。
これが何の研究プロジェクトで、今後何が出来上がるのか、それは今後の苦しみ・・・ではなくお楽しみ、ということで!
ページトップへ
- 1月4日(月) 門松続き
夕方にはデコレートされ本格的でおしゃれな門松となり教育棟の入り口に飾られていました。
今年もどうかよい一年になりますように。。。
ページトップへ
- 1月4日(月) あけましておめでとうございます。
- 堤です。今年もどうぞ宜しくお願い致します。
写真は昨年末の風景。
28日の午後2時半には竹でしたが、、、
ページトップへ
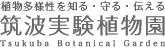
![]()














