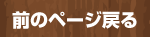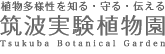| ホーム ≫ 学習 ≫ 学習支援プログラム ≫ 植物園でSDGsを学ぼう! ≫ テーマ:カカオ ≫ カカオ豆生産とカカオ農家支援の取り組み |
カカオ豆生産とカカオ農家支援の取り組み
つくば市内に本社工場がある東京フード株式会社の皆様に、カカオ豆生産とカカオ農家支援の取り組みについてお話をお伺いしました。
取り組みをはじめたきっかけを教えてください
私たちの親会社である月島食品工業(株)の創業者である橋谷亮助が、インドネシア、スラウェシ島のゴロンタロ州に滞在経験があり、インドネシアへ強い思い入れがあり、インドネシアの留学生を支援する橋谷奨学会を設立しています。
この奨学生のOBの一人から、「ゴロンタロ州の森林保全のためにカカオの木を増やしていきたいが、収穫したカカオ豆を買ってくれるところを探している。現地のカカオ豆の品質が向上して買ってくれるところが増えれば現地農民の生計改善にもつながる。」と相談を受けたことがきっかけです。
当初はSDGsなど社会貢献といった発想はなく、ゆかりある人が困っているため、好循環を生み出せるようチェーンをまわせる手伝いができたらと考えてはじめました。後になって、この取り組みがSDGsにつながることに気がつきました。
企業の社会貢献からはじまったのではなく、シンプルな人助けの気持ちからはじまったのですね。
どのような取り組みをされていますか?
2016年からインドネシアにおける支援活動を開始しました。
手間をかけて良いカカオ豆をつくっていただき、適正価格での購入を目指して、以下のことを実施しています。
- カカオ栽培のアグロフォレストリー*の推奨
*農業アグリカルチャーと林業フォレストリーの合成語で、森を管理しながら森の中で農作物を育てる農法 - 現地のカカオ生産技術支援(防虫の袋掛けなど)
- 現地でのカカオ生産増加支援(カカオの苗木の配布など)
- 発酵技術支援(チョコレートらしい風味をつくる為に必要。これまではきちんと発酵させずに出荷することが多かった。)
- 農家の生計改善
- 農家の働きがい向上
- 整備面での支援(散水ポンプの整備など)
取り組みといってもさまざまで、栽培技術に限らず、発酵技術、農地整備、働きがい向上・・・多角的な支援が必要なのですね。
インドネシアでの活動地域を教えてください。
インドネシアのスラウェシ島北部、ゴロンタロ州ボアレモ県というところです。スラウェシ島にある6つの州の中では、貧困率が最も高いとされる地域です。
取り組みを進める上で、大変だった点を教えてください。
農家さんとの信頼関係が最も重要で、信頼関係を築くまでが大変でした。一緒に作業をして、収入改善の手伝いや農地整備も行い、心を通わせて、協力農家を増やしてきました。農業全般に言えることですが、1年では栽培改善は難しく、長期的な取り組みが必要です。地道な活動ですし、現地の言葉でのコミュニケーションが必要で、非常に大変でした。現地の関連会社などの協力もあって、今では良好な信頼関係が築かれています。
継続的な活動が実を結んだということですね。長い時間をかけた大変なご苦労があったことでしょう。
取り組みを進めてよかったと思ったことを教えてください
現地の協力農家さんが増えた(25軒ほどになった)ことです。
また、状態よい発酵したカカオ豆が入手できるようになるなど、うまくいったときですね。
これまでの苦労があったからこそですね!
取り組みを始めて、会社の中でどのような変化があったか教えてください。
- イベントなどで社会発信することが一般の方との接点になった。
- 地元の方に楽しんでもらえていると感じること。
- 国立科学博物館の筑波実験植物園など外部との付き合いができ、外部との接点が増えたこと。
色々とありますが、以下の3つが挙げられます。
取り組みによって、また別の活動に広がり、新たな関係も生まれたのですね。
同じ製菓業界や関連会社の取り組みや姿勢についても教えてください。
- SDGsに関連する取り組みは、大手企業などは先んじて取り組んでいると思われます。
- チョコレート業界では調達方針として、特にカカオについて、いかにサステナブルなものを取り入れるかという取り組みが進んでいると感じています。
- 中小企業でも、同じような取り組みをしている企業も多いです。同じくインドネシアで活動する有志同士で、情報共有など協力することもあります。
今後の課題、そして今後目指すことを教えてください。
- まだ道半ば、長期的な継続が問題で、活動の長期継続を目指したいと考えています。
- 現地政府の方針や政策にも大きく左右されるため、農業政策によるの支援の有無で現地農家の生活は大きく変わっていきます。一企業の活動では限界があり、現地政府等との連携が必要です。
- 化学薬品を使わない無農薬のカカオ栽培支援や、肥料をオーガニックにつくるような取り組みを通じて、自分たちで循環できるようなシステムの確立にも取り組んでいます。たとえば、ガマルという植物を育て、葉はヤギの餌とし、ヤギのフンなどをアグロフォレストの肥料とすること。ヤギや牛のフンによる堆肥づくりで発生するガスを火力とすること。カカオポッドやトウモロコシの芯を炭として廃棄物を減らして循環させること、などの支援にも取り組んでいて、このような活動を通じて、現地の農家が自分たちで循環できるよう支援していければと考えています。
長期的な取り組みの継続には、農家さんの自立が重要なのですね。今後に向けて人材育成も必要で、現地での教育支援なども重要と考えられますね。
最後に、中高生の皆さんにメッセージを聞かせてください!
塩見さん:ぜひ現地をみて、実体験して学んでほしいです。その際に現地のおいしいものもぜひ食べて欲しい。日本ではほぼ流通していないカカオパルプは現地でなら食べられます。カカオパルプも、年によって、木によって味がちがい面白いので、体験してみてください。
本麻さん:現地では生きているということを実感できることも良い点です。日々の体調管理が重要で、日が登り日がくれるまで働くことで、生きていると強く感じられます。あとドラゴンフルーツなど日本では珍しい果物がいくらでも食べられるところもオススメです。
中島さん:現地でしかわからないこと、楽しいこと、発見があり、勉強になります。
またカカオはとても奥が深い植物です。チョコレートになるまでの工程は長く、いろいろな部分を見ていくのも楽しいと思います。品種改良ほか、取り巻く環境改善など、やれることはたくさんあるので、興味を持ってくれたら嬉しいです。
みなさんには若いうちにいろいろ体験や経験を積んでもらいたい、ということですね!
本日は貴重な取り組みをご紹介いただきありがとうございました!
取り組み紹介HP
東京フード株式会社(※外部サイト)