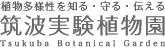植物名 |
フジ(ノダフジ) |
||
|---|---|---|---|
学 名 |
Wisteria floribunda (Willd.) DC. |
||
科 名 |
マメ Fabaceae/Leguminosae |
||
旧科名 |
マメ FABACEAE |
||
園内の花 |
|
||
解 説 |
つる性の落葉木本。つるは上方向に左から右へ巻く、はじめ褐色の短毛を密生し、後に無毛となる。葉は長さ20-30cmで、11-19枚の長さ4-10cmの小葉がついている。葉質は薄く全縁。花序は頂生し、下垂して長く伸び、時に100cmに達する。多くの藤色・紫色または淡紅色の花をつけ、花序の軸には小花柄とともに白色の短毛が密生する。豆果は狭倒卵形で扁平、長さ10-19cmでビロード状に短毛を密生させ果皮は厚く、熟して木質となる。冬季に乾燥すると2片に裂けながらねじれて、扁平で円形、褐色で光沢のある種子を飛び散らせる。低山地や平地の林縁・崖・林中に分布。 |
||
研究者ノート |
フジの葉は、どれが1枚の葉だろうか、思案することもあるでしょう。そんな時は葉あるいは柄の付け根(葉腋)に芽があるかどうかを調べるのがよいでしょう。もしあれば、そこから先全部が1枚の葉であり、細かく切れていても1枚1枚は葉片ということになります。フジはそんな例です。それに対し、ツツジやサクラなど多くの植物では1枚の葉の付け根に芽があります。このように、葉の根元にはふつう腋芽ができるという規則性があるので、そのあるなしで葉が複葉か単葉か区別できるのです。(加藤雅啓) |
||
自然分布 |
本州・四国・九州 |
||
絶滅危惧ランク |
|
||
日本固有 |
○ | 筑波山分布 |
○ |
利 用 |
フジの繊維は非常に丈夫なため繊維・いす・籠に使われる。樹木に絡みつき木を変形させるので植林地では見ることはできない。世界遺産である「古都奈良の文化財」の一つ春日大社境内に「春日大社の砂ずりの藤(奈良県奈良市春日大社境内)」というフジがある。地面の砂をすりそうなまでに長く垂れ下がる姿は美しい。 |
||
名前の由来 |
ノダフジの名は牧野富太郎によりフジの名所である大阪市福島区野田にちなんでいる。 |
||
園内区画 |
|
||
「おすすめ」 |
14 |
||