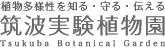植物名 |
アマギカンアオイ |
||
|---|---|---|---|
学 名 |
Asarum muramatsui Makino var. muramatsui |
||
科 名 |
ウマノスズクサ Aristolochiaceae |
||
園内の花 |
|
||
解 説 |
タマノカンアオイによく似た常緑の多年草。茎は円く、地をはい、傷つけると芳香を出す。緑色の柄があり、葉は卵型あるいは長楕円形で長さ5~8cm、基部は深い心形。表面には強い光沢があり、鮮緑色でまれに紫色を帯びることがある。葉脈は著しくへこむ。葉柄の基部から短い柄を出し、径約2cmの花を横向きにつける。萼は鐘形で長さ約1cm、筒部の先はややくびれる。萼裂片は縁が著しく波打つ。花期は5月。 |
||
研究者ノート |
[カンアオイの仲間]徳川の家紋で有名なフタバアオイの仲間で寒い時期に青々と茂ることから寒葵の名があります。なんと日本に50種以上がありますが、多くは絶滅の危機に瀕しています。カントウカンアオイやクワイバカンアオイといった種は冬咲きで、葉に隠れるように地面すれすれに花をつけます。花は赤紫や茶色で、まるでたて穴のような非常に不思議な姿をしています。一部の種ではキノコに擬態しているとも言われており、キノコと間違えたキノコバエの仲間が花の内部にあるひだに卵を産みにやってきて、その時に花粉が運ばれることが知られています。(奥山雄大) |
||
自然分布 |
本州(伊豆半島、山梨県) |
||
絶滅危惧ランク |
絶滅危惧Ⅱ類 (VU) |
||
日本固有 |
○ | 筑波山分布 |
- |
名前の由来 |
和名は伊豆天城山で発見されたことにちなむ。 |
||
園内区画 |
|
||
「おすすめ」 |
0 |
||