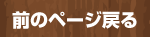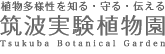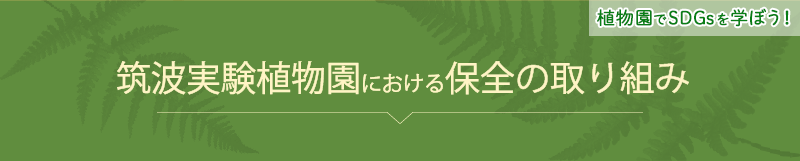| ホーム ≫ 学習 ≫ 学習支援プログラム ≫ 植物園でSDGsを学ぼう! ≫ テーマ:絶滅危惧 ≫ 筑波実験植物園での絶滅危惧植物保全の取り組み |
筑波実験植物園での絶滅危惧植物保全の取り組み
筑波実験植物園で絶滅危惧植物の研究に取り組む國府方先生にお伺いしました。
筑波実験植物園ではどのような絶滅危惧植物の発信をしていますか?
常設展としては、絶滅危惧植物コーナー、琉球の絶滅危惧植物を多く展示した多目的温室などがあります。その他にも植物園のいたるところに絶滅危惧植物を植栽展示しています。また、研修展示館や教育棟には絶滅危惧植物関連の展示パネルなどがあります。
さらに、絶滅危惧植物シリーズの企画展を植物園で毎年一回開催しています。
絶滅危惧植物の保全で苦労することは?
何といっても、栽培です。
筑波実験植物園で保全している絶滅危惧植物はそれぞれに適した栽培環境があり、それを見極めることは難しいです。また、挿し木などで採集された植物を温室などで活着させることは試行錯誤の繰り返しです。植物園で皆さんに見て頂いている絶滅危惧植物は植物園バックヤードのスタッフの絶え間ない努力の賜物なのです。
筑波実験植物園ではどのような種類の絶滅危惧植物を保全していますか?
シダ植物、ラン科植物、水草、高山植物、亜熱帯島嶼部である小笠原諸島や琉球列島の植物などをコレクションとして保全しています。
どうしてそれらの種類を保全しているのですか?
シダ植物、ラン科植物、水草は絶滅危惧植物を多く含み、高山植物、亜熱帯島嶼部は絶滅危惧植物が集中する地域です。よって、これらの絶滅危惧植物を積極的に守る必要があります。筑波実験植物園にはそれぞれのスペシャリストがおり、知識を活かして絶滅危惧植物を保全しています。また、保全している植物をもとに植物多様性に関する研究も行っています。
植物園は植物を展示するだけではないのですね。
はい、多くの人に植物をみて楽しんで、学んで頂くこととあわせて、植物を栽培することで保全し、その栽培している植物をもとに研究することも植物園の大切な役割です。
そのことから、筑波実験植物園では、「植物多様性を知る・守る・伝える」を命題としています。
どのような研究をしているのか教えてください。
特に絶滅危惧植物を分類学的に正しく把握するための研究を行っています。例えば、これまで1種類と思われていた絶滅危惧植物が本当は2種類だったとか、これまで海外との共通種と思われていた植物が本当は日本の固有種だったとかという研究例があります。これらの分類データは絶滅危惧植物を守るための大切な基礎データとなります。
また、絶滅危惧植物と昆虫との関係、絶滅危惧植物の化学特性に関する研究も行っています。これらは絶滅危惧植物を自生地で守るための大切なデータとなります。
私たちも絶滅危惧植物の保全に関わることができますか?
はい、できます。
現在では、ある地域の生物や環境を守る市民サークルなどが活発に活動しています。そのようなサークルに参加することで、植物だけでなく、生物や環境を守ることができます。また、多くの市民団体には生物や環境に詳しい方がおり、一緒に活動するといろいろなことを教えてくれて勉強にもなります。
最近、地球温暖化が問題になっています。この地球温暖化によって絶滅危惧種になってしまう生物もいます。例えば暑さに弱い高山植物は夏でも涼しい環境でかろうじて生きています。そのような植物は夏の異常高温によって深刻なダメージを受けます。よって、エコバックの利用などエコな活動は地球温暖化を抑えることに貢献し、延いては絶滅危惧生物の保全に貢献します。